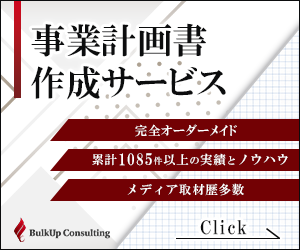アメリカを震源とする株価低迷・インフレ、止まらない円安、泥沼化しているウクライナ情勢等で日本経済は現在大変厳しい状況にあるといえます。
そんな逆風の中でも健闘し資金調達を実現しているスタートアップ企業もありますが、資金調達成功のポイントは事業計画書の書き方にあります。
(目次)
1.国によるスタートアップ支援策
2.スタートアップの資金調達状況
3.スタートアップを支援する投資家の種類
4.スタートアップを成功させる事業計画書の書き方
※参考:スタートアップ・ベンチャーにおける今後の注目業界
1.国によるスタートアップ支援策
令和4年11月24日、岸田総理は、総理大臣官邸で第3回スタートアップ育成分科会に出席しました。その中で、次のような内容を述べています。
・スタートアップ育成5か年計画をまとめ、新しい資本主義実現会議で決定する。
・この計画を実行することにより、日本をアジア最大のスタートアップハブとする。
・そのための目標として、スタートアップへの投資額を、現在の8,000億円規模から5年後の
2027年度には、10兆円規模と10倍増にする。さらに、将来において、ユニコーンを100
社創出し、スタートアップを10万社創出することを目指す。
・目標達成に向け、3本柱の取組を一体として推進していく。
①スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
起業経験者が助言役となるメンターによる支援事業の育成規模を年間70人から5年後に500
人に拡大する。あわせて、海外に起業家育成の拠点となる『出島』を創出し、5年間で1,00
0人規模の若手人材を派遣するとともに海外トップ大学の誘致によるグローバルスタートアップ
キャンパス構想を実現する。
②スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化を図る
創業者などの個人が、保有する株式を売却してスタートアップに再投資する場合の優遇税制を
整備し、ストックオプション税制の権利行使期間の延長も行う。
③既存の大企業からスタートアップへの投資を図るオープンイノベーションの推進
スタートアップの成長に資するものについて、スタートアップの既存発行株式の取得に対しても
税制措置を講ずる。
尚、今年になってからの国によるスタートアップ支援の動きは以下のとおりです。
2022年6月:「METI Startup Policies ~経済産業省スタートアップ支援策一覧」公表
2022年8月:スタートアップ企業への支援策を拡充
スタートアップ支援政策を推進する担当大臣設置
2022年9月22日:岸田首相はニューヨーク証券取引所(NYSE)で講演しましたが、その中
で日本の5つの優先課題を紹介しています。
①人への投資
・大きな付加価値を生み出す源泉となる人的資本への投資
②イノベーションへの投資
・人工知能(AI)、量子、バイオ、デジタル、脱炭素、スタートアップ 等
③グリーントランスフォーメーション(GX)への投資
・2050年のカーボンニュートラル実現
④資産所得倍増プラン
・個人向け少額投資非課税制度(NISA)の恒久化
⑤世界と共に成長する国づくり
・世界に開かれた貿易・投資立国
閉塞感のある日本企業・日本経済を活性化する為にも、スタートアップの活躍を強力に後押しすることが、一連の政府支援策の狙いであるといえるでしょう。
(人材教育に力を入れる東京都)
小池百合子都知事は2022.11.24に「グローバル・イノベーション・ウィズ・スタートアップ(Global
Innovation with STARTUPS)」という施策を発表しました。政府も28日にスタートアップの育成
強化に関する5カ年計画を正式発表しています。
(出典:東京都 「Global Innovation with STARTUPS」)
http://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/wp-content/uploads/Global-Innovation-with-STARTUPS3.pdf
2.スタートアップの資金調達状況
株価低迷、インフレ進展、止まらない円安、泥沼化しているウクライナ情勢等、世界的に経済が混迷する中で、日本のスタートアップ・ベンチャー企業の資金調達状況も厳しい状況となっています。
2022年上期の国内スタートアップ資金調達額は4,160億円で昨年の調達額の約50.6%となっていて半期だけみると昨年よりも上向きですが、調達社数は半数に達していません。つまり1社あたりの調達額が大型化している傾向となっています。
世界情勢の影響が徐々に日本の資金調達環境にも変化をもたらしてきていて、レイターステージ(株式上場も視野に入る成熟段階)のベンチャーも企業評価額の水準が下がってきていて、IPO直前でとりやめるケースも多くなってきています。
投資家によるベンチャー企業の投資可否の選別がより厳しくなってきていると思われます。
そんな中でも、事業環境がよく独自の強みをもっている企業は着々と大型の資金調達を成功させています。投資ファンドの設立も2019年~2021年にかけては活発だったので、未投資の運用金額は豊富と思われます。(ファンドの投資期間は通常2~3年)
VC等に出資する機関投資家も広がっていて、世界最大の機関投資家であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)もVCへの投資を増やす動きをみせています。
又、政府も上述のとおり「スタートアップ創出元年」を打ち出していて、スタートアップ・ベンチャーへの投資環境は揃ってきているといえるでしょう。
独自の強みを持ち事業の採算性が高い等、事業環境の良い企業はこの逆風の中でも資金調達のチャンスがきたといえるでしょう。
3.スタートアップ・ベンチャー投資家の種類
|
資金提供者・形態 |
概要 |
|
他企業からの出資 |
外部企業との提携、株式一部譲渡など。 ベンチャーの事業が自社の事業に関連する場合が多い。事業育成やシナジー効果も。 |
|
VC(ベンチャーキャピタル) |
投資会社(金融機関、機関投資家、一般企業、自治体等から資金を集め、ベンチャーに出資して運用する)からの出資。コンサル支援も行う。 |
|
CVC(コーポレートVC) |
一般企業が自社の資金をベンチャーに投資する際にベンチャーキャピタルを設立してファンドを組み、投資・運用する。運営は外部委託も。 |
|
エンジェル投資家 |
個人投資家(成功者が多い)による起業家への出資 |
|
(クラウドファンディング) |
インターネットなどを通じた資金調達 |

4.資金調達を成功させる事業計画書の書き方
スタートアップを支援するいずれの資金提供者も、対象企業に事業開始用資金を提供し財務体質の改善等を期待するのと同時に対象会社健全育成のうえ、将来的に各種利益(インカムゲイン、キャピタルゲイン等)を得ることを目的としています。
従って、借り手企業についてはシビアに調査・分析するのは必然といえます。
借り手企業の財務状態や将来性を判断する材料として、決算書やその他の経営状態を確認する多数の書類に加えて、将来の事業の姿を可視化・文章化したものである「事業計画書」が大きな役割を果たします。
とくにスタートアップ・ベンチャー企業の事業計画は、過去の実績はありませんので、その事業目論見が客観的に納得性があり実現性のあるものでなくては、信頼できません。希望的な数字だけで作成した場合はすぐにわかりますので、事業計画書全ての項目に対して裏付け・根拠のあるものにする必要があります。
まさに資金調達の決め手は「実現性のある事業計画書」と経営者のプレゼン能力(熱意、覚悟)にあるといえるでしょう。
<事業計画書の書き方>
事業計画書とは、会社の事業コンセプト・企業戦略・事業内容・組織体制・運営方法・行動計画・売上や利益等の数値目標などを記載した書類(計画書)のことです。
投資家から資金調達する時や社内に今後の事業計画を説明・周知する際に利用します。
事業計画書の書き方については、当ブログ内に詳細な内容の記事がありますので、以下のページをご参照下さい。
-事業計画書の書き方&活用- (基本知識)
※プロ集団である資金提供者を納得させるような事業計画書を作成することは、大変困難な作業となります。それなりの経験と知識及びテクニックが必要となりますので、外部の事業計画書作成の専門家(コンサルタント)の活用も一つの方法といえるでしょう。
※当バルクアップコンサルティング社は、全員が日本及び世界のトップコンサルティングファームで経験を積んだトップコンサルタントであり真のプロフェッショナル集団です。
スタートアップを計画されていて、資金調達や事業展開にお悩みの場合は是非一度ご相談下さい。
バルクアップコンサルティング株式会社
<参考:スタートアップ・ベンチャーにおける今後の注目業界>
今後成長を見込めるスタートアップ・ベンチャーのうち、有望とされている業界をあげてみました。
(今後、経済情勢・地球環境・技術の進展等により刻々と変化していくと思われます)
1.IT業界
1)Web3(ブロックチェーン技術を応用したサービス群)
・NFT(非代替性トークン)、DeFi(分散型金融サービス)、”Play to Earn”(ゲームをする
ことで報酬を得られるサービス)、DAO(ブロックチェーンを応用した自律分散型のビジ
ネス組織) など
2)サイバーセキュリティ(年率約10%での成長予想)
・コロナ禍でリモートでの仕事や授業が増え、インターネットに接続する機会が増えたこと
で、サイバー攻撃も拡大・複雑化
3)デジタルマーケティング(Web広告の成長は2022年以降も継続)
・インターネットを利用するすべて(スマホ、PC等)のマーケティングを含む
4)DX(デジタルトランスフォーメーション)
・IoT(Internet of Things/モノのインターネット)
・AI(Artificial Intelligence/人工知能)
・5G(第5世代移動通信システム)
・クラウド
2.EC業界/倉庫・物流業界
2022年以降もECの利用者は増え、生活に身近な日用品や食品といったEC化率が低かった分野
も伸びる予想。EC業界の発展に伴い、倉庫・物流業界もさらに成長するでしょう。
3.ESG(環・社会・企業統治)
ESG投資は、「業績」や「財務状況」など財務情報ではない側面を考慮して投資先を選ぶ
ことを指します。
Environment(環境):二酸化炭素排出量の削減、再生エネルギーの使用 など
Social(社会):職場環境における男女平等、ダイバーシティ など
Governance(ガバナンス):情報開示や法令順守 など
4.モビリティ
自動車による移動や運搬をスムーズに行う
・EV(電気自動車)
・自動運転
・MaaS(Mobility as a Service)
・オンデマンド交通
・ドローン、自動配送ロボット
・空飛ぶクルマ
5.宇宙
わが国をはじめ世界各国ではスタートアップが宇宙分野に参入し、新たな宇宙機器産業や宇宙
利用産業が創出されています。
・宇宙旅行(「Space X」「Blue Origin」)
・通信衛星(「Starlink」:世界中にインターネットを届ける)
・各国自前の観測衛星(リモートセンシング:防災、安全保障、農業・漁業、金融、観光など)
・宇宙空間に「携帯基地局」設置(ネット人口の飛躍的増大)
・民間宇宙船(「Crew Dragon」)
・軍事衛星(アジア太平洋地域は、2021年から2027年の期間において、最も高い成長率を示す
と予想されています)
6.医療業界
・ヘルスケア(GAFAも積極的に投資。2022年以降も成長)
・ワクチン関連(新型コロナウイルスのワクチン関連分野)
7.農業業界
・「スマート農業」(AIやドローンを駆使)
・「アグリテック」(農業とテクノロジーのを組み合わせ)
日本における労働人口の低下、農業の担い手不足を解決するカギ。
・「D2Cサービス」(EC業界との組み合わせ、生産者と消費者を直接つなげる)